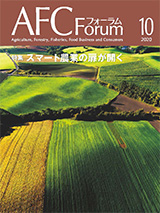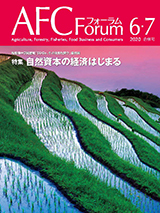- ホーム
- 刊行物・調査結果
- 農林水産事業 AFCフォーラム、アグリフードサポート、情報戦略レポート
- 農林水産事業 AFCフォーラム(2020年)
農林水産事業 AFCフォーラム(2020年)
2020年12月号「どう継ぐのか、生産基盤」
特集
どう継ぐのか、生産基盤
【特集1】
- 協業法人を設立し事業承継の不安解消
東宗谷農業協同組合 代表理事組合長/佐藤 裕司
多額の資産を引き継ぐ畜産では、事業承継時に地域の支援が必要となることが多い。地域酪農基盤維持に向け、事業承継支援に積極的な農協が取り組みを語る
【特集2】
- 農家の事業承継を支援する食鳥企業
貞光食糧工業株式会社 代表取締役社長/辻 貴博
深刻な後継者不足に悩む中山間地域で養鶏農家の承継に力を注ぐ食鳥企業がある。地縁のない就農希望者を受け入れて育て、後継者として地域農家との間を取り持つ
【特集3】
- 畜産業の事業承継を円滑に進めるには
経営コンサルタント・上級農業経営アドバイザー/村上 一幸
農業における経営継承のなかでも畜産業の経営継承は、承継資産が多額で経営上のみならず税務上の対応にも迫られる。この問題に精通した専門家からのアドバイス
巻頭言
- 日本産のワイン
玉村 豊男/エッセイスト・画家・ワイナリーオーナー
連載
農と食の邂逅
- ナカバヤシ株式会社 兵庫工場/兵庫県
足立 渚沙・兼藤 夢
製本企業が、特区を利用してニンニク生産を開始した。若い女性2人が携わる。一人は丁寧な作業でまっすぐな畝をめざし、もう一人は、畝に込められた気持ちを伝えたいと話す
変革は人にあり
- 株式会社有田牧場/熊本県
有田 耕一
出会った門外の人々から学んだことを肉用牛経営に生かし規模拡大。独自の工夫を重ねて自家牛群の改良に取り組み、付加価値の高い肉用牛の繁殖を志す
新・農業人
- アスパラマル株式会社/長野県
吉見 雅史
本来、アスパラガス栽培に適さない川の跡地で掘れば石がごろごろと出てくる粘土質の田圃を使い、大規模安定経営を実践する
オピニオン・レポート
情報戦略レポート
- 景況感はコロナ禍で大幅に悪化
担い手農業者は高い投資マインド
―農業景況調査(2020年7月調査)―
フォーラムエッセイ
- 記憶を味わう
俳人 大高 翔
耳よりな話 222回
- 飼料生産と気象リスク
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構畜産研究部門 飼料作物研究領域長
奥村 健治
地域再生への助走・特別編
- 古代染色植物の日本茜を地域資源に農と伝統工芸の関わりを復活させる
美山日本茜研究会/京都府南丹市
渡部 康子
書評
- 『石川三四郎 魂の導師』
百姓・思想家 宇根 豊
インフォメーション
- AFCフォーラム総目次(2020年1月~12月)
- セミナーやオンライン相談会で農水産物の輸出を支援しています
佐賀支店・本店 - 若手職員が集い農林漁業の将来を議論
本店 - みんなの広場・編集後記
農業経営アドバイザー
TiDBit
- 二人の言葉が示す 新規就農者 五つの心得
株式会社YACコンサルティング 古髙 伸一
1月号予告
- 特集は、「ウィズコロナの農業・食品産業」を予定。
新型コロナウイルスの感染拡大は、観光、外食、輸出産業に大きな打撃を与え、農林水産分野では、高級食材や花きをはじめとして全業種に影響があります。農業・食品産業および地域が直面する課題を明らかにし、状況変化を受け改善策として求められるものとはなにか考えます。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2020年11月号「水田農業・承継のカタチ」
特集
水田農業・承継のカタチ
【特集1】
- 親子間の考え方の違いを乗り越える
有限会社フクハラファーム/福原 昭一・悠平
親から子への経営承継は一般的と思われるが、考え方が相違し意見が合わないなど難しさを伴う場合も多い。現在まさに、親子間で承継を進める稲作経営体に話を聞く
【特集2】
- 若者を育成雇用し、地域農業を維持
青山 浩子/新潟ひかりっこ株式会社
地域の大規模な稲作経営体など第三者が農業を継承するのも、事業承継の姿。米どころ新潟で地域農業の受け皿の役割を果たす、大規模稲作経営体を紹介しよう
【特集3】
- 中山間集落の維持へ多様な取り組み
山田 優/農事組合法人寺内農場・農事組合法人やまとだに
地域の基幹産業としての農業の承継は、高齢化が進む中山間集落では難題だ。鳥取県南部町にある二つの農業法人が選んだ道から、地域農業を守るためのキーワードが見えてきた
情報戦略レポート
- コロナ後の課題は需要の変化に対応した商品開発
―食品産業動向調査(2020年7月調査)―
経営紹介
新・農業人
- AGRIMOON/島根県
柴原 信行
サラリーマンが家庭菜園をきっかけに本格的に農業に足を踏み入れた。人と違った作目を求め、たどり着いたエゴマで、農業独り立ちをめざす
変革は人にあり
- 株式会社KAWACHO RICE/青森県
川村 靜功
米袋をペットボトルに変え、新たな売り方で米の需要を呼び込んだ。「すべて米から始まる」をスローガンに、青森から世界へ、米と地域食材を発信する
シリーズ・その他
観天望気
- 農業資源のバトンパス
柚木 茂夫/一般社団法人全国農業会議所 2
農と食の邂逅
- オーガニックファーマーズ名古屋/愛知県
吉野 隆子
有機玄米菜食で体調が改善、食への関心から農の世界へ。農業者にも消費者にもオーガニックを身近な存在にし、農業を始めたい人がやれるよう応援していくことが私の仕事 19
主張・多論百出
- 多様な人材が農業の成長産業化を促す
次世代の心を捉え、チャレンジする力を
一般社団法人アグリフューチャージャパン
合瀬 宏毅 25
フォーラムエッセイ
- 石垣の海で見たもの
ココリコ 田中 直樹 30
まちづくりむらづくり
- 日本最北の農業高校がめん羊飼育
生徒の熱意が地域を元気にする
北海道遠別農業高等学校/北海道遠別町
石川 ウーリーエル 31
書評
- 『100歳まで元気でボケない食事術』
NPO法人食材の寺小屋 青木 宏高 34
インフォメーション
- 国産農水産物の展示商談サイト
「アグリフードEXPOオンライン」のご案内 35
みんなの広場・編集後記 37
TiDBit
- 生産者のありたい姿を実現する
株式会社食農夢創 仲野 真人 38
12月号予告
- 特集は、「事業承継最前線/畜産経営」を予定。
喫緊の課題である事業承継について、次号では畜産経営を取り上げる。畜産は、耕種に比べ承継費用が多額となりがち、環境面から新規の農場開設が困難といった特徴から、家族内承継に加え、M&Aなどの事例も出てきている。畜産の事業承継に求められるものとは何か、考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2020年10月号「スマート農業の扉が開く」
特集
スマート農業の扉が開く
【特集1】
- もうかるビジネス、住みやすい農村へ
三輪 泰史
スマート農業は「匠の眼・頭脳・手」として活用できる。労働力不足や技術習熟度の向上など、日本農業の直面する課題解決の切り札となり、農村の暮らしを変革する可能性を秘める
【特集2】
- 自動化・無人化。次世代農業技術開発
飯田 聡
農機とICTの融合により、農機の完全無人化など新しい水田農業のカタチが期待される。次代を見据え開発に取り組む農機メーカーが描く、スマート農業・農村の未来像
【特集3】
- フードチェーン視野に北海道農業展望
野口 伸
耕地面積が大きい北海道では、スマート農業の効果が発揮されやすく導入や実証実験が進む。そこでロボット工学第一人者に北海道の事例からスマート農業発展の道筋を語ってもらった
特別緊急企画
- コロナ禍における農林水産物・食品輸出
その動きとジェトロの支援策
中 裕伸
コロナ禍によって日本産農林水産物・食品を取り巻く輸出環境は激変した。需要構造の変化は海外での新ビジネスを生む可能性がある
経営紹介
変革は人にあり
- ファロスファーム株式会社/大阪府
竹延 哲治
世界と戦える高い生産性を支えるのは、データ重視の「病気と闘わない」「養豚を科学する」経営。国内養豚出荷シェア2%を視野に入れ、日本で一番たくさん食べられる豚肉をめざす
新・農業人
- 有限会社ジェイ・ウィングファーム/愛媛県
大森 陽平
地域から厚く信頼されていることが評価され、就農7年目で事業承継を見据え取締役に就任。「農業で地域を守る」を信念とし、より多くに裸麦を知ってもらおうと奮闘中だ
シリーズ・その他
観天望気
- スマート農業は技術の掛け算 湯川 智行 2
主張・多論百出
- フリーフロム株式会社 山﨑 寛斗 17
農と食の邂逅
- 鈴木 佐江子・希巳江/静岡県
片柳 草生(文) 河野 千年(撮影) 19
フォーラムエッセイ
- 夏の思い出 内田 恭子 22
耳よりな話 221回
- 温暖化がもたらす新たな機会 杉浦 俊彦 26
まちづくりむらづくり
- 小さな村に大きな夢を実現する
夫婦が手づくりの里山体験施設
ケロンの小さな村/石川県能登町
上乘 秀雄 27
書評
- 三次 理加 著
『お米の先物市場活用法』
武本 俊彦 30
インフォメーション
- 販路の多角化へ取り組む皆さまへ
「#元気いただきますプロジェクト」のご紹介
農林水産省 33 - リスクマネジメント研修で講師を務めました
帯広支店
「アグリフードEXPOオンライン」開設のお知らせ 35 - 新型コロナウイルス感染症・令和2年7月豪雨に係る特例制度が措置されています 36
みんなの広場・編集後記 37
TiDBit:上級農業経営アドバイザーのこぼれ 連載6号
- 経営にゴールなし
支援者がいれば困難越え成長する
古賀 久子 38
11月号予告
- 特集は、「事業承継シリーズ 前篇~稲作経営~」を予定。
日本の基幹的農業従事者数のうち約7割が65歳以上と高齢化が進み、後継者不足が深刻化する状況で、喫緊の課題の一つに事業承継が挙げられます。そこで2回に渡り、耕種、畜産における事業継承を考えます。前篇では、水田農業の事業承継のヒントを探ります。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2020年9月号「持続する水産業への視点」
特集
持続する水産業への視点
【特別寄稿】
- 水産業の未来に向けて
長谷 成人
約70年ぶりとなる漁業法の改正を柱に水産政策の改革を推し進め、水産業振興の舵を取った前長官によるわが国漁業の発展へ向けた熱いメッセージ
【特集1】
- 調理済み魚の直販で挑戦する水産加工
小澤 弘教
日本人の水産物消費量は減少しているが、手軽に食べられる魚商品の売れ行きは好調だ。消費者ニーズをつかみ、新たな市場を創った水産加工業者の取り組みを追う
【特集2】
- 「海と生きる」漁業者が協業し課題に挑む
鈴木 一朗
収益の悪化、船舶の老朽化、後継者不足など、多くの課題を抱え衰退の一途だった気仙沼の近海まぐろはえ縄漁業。震災を乗り越え事業を再生した漁業者たちの奮闘ぶりに迫る
【特集3】
- 「豊洲市場」が担うべき新たな役割
小松 正之
世界最大の消費地卸売市場である東京都の豊洲市場は、日本の水産業・流通業の将来を見据えた斬新な役割を追求すべきだ
情報戦略レポート
- コロナ下で調理時間増える
食の志向は経済性志向が上昇
―消費者動向調査(2020年7月調査)―
経営紹介
変革は人にあり
- 株式会社長崎ファーム/東京都
良川 忠必
ふぐ料理専門店を経営する東京一番フーズが養殖事業に進出。安心・安全な魚を提供する垂直統合型の総合水産企業をめざしながら、地域の水産業の振興にも力を注ぐ
シリーズ・その他
観天望気
- 「スマート」な水産業 宮下 和士 2
主張・多論百出
- 有限会社フード・サポート 細川 良範 23
フォーラムエッセイ
- 奈留島のある漁師さん 村上 康成 28
まちづくりむらづくり
- 加工品開発、オーナー制度に自主製作映画
トマト農家の女性たちが地域の元気を育てる
企業組合遊子川ザ・リコピンズ/愛媛県西予市
辻本 京子 29
耳よりな話 220回
- 大規模施設園芸の運営に4つのポイント 田口 光弘 32
書評
-
金子 修治・鈴木 紀之・安田 弘法 編著
『博士の愛したジミな昆虫』
宇根 豊 33
インフォメーション
- 人をつなぐノウハウを活かし産業間の人材マッチングを後押し
札幌支店 34 - 日本政策金融公庫農林水産事業業務報告会を開催
情報企画部 34 - 農林水産物・食品の輸出・海外展開に取り組む方に
新たな資金制度ができました
融資企画部 35 - 新型コロナウイルス感染症・令和2年7月豪雨に係る
特例制度が措置されています 36
みんなの広場・編集後記 37
TiDBit:上級農業経営アドバイザーのこぼれ話
- 数字に強い本物の農業経営を 工藤 秋一 38
10月号予告
- 特集は、「スマート化が導く農業・農村の未来」を予定。
政府は「2022年度までに様々な現場で導入可能なスマート農業技術が開発され、農業者のスマート農業に関する相談体制が整う」ことを目標としている。農業のスマート化により何が変わるのか。スマート農業の最新事情を探り、次世代の農業・農村の姿を展望する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2020年8月号「業務用取り戻す国産野菜」
特集
業務用取り戻す国産野菜
【特集1】
- 野菜の需給をめぐる構造的課題と対応
佐藤 紳
利便性・簡便性重視の志向変化に合わせ国内シェアを伸ばす加工・業務用野菜だが、その3割は輸入野菜が占める。国産野菜がシェアを奪還する方策とは。産地の抱える課題から考察する
【特集2】
- 野菜生産サプライチェーンと持続経営
松田 恭子
取り組む者が増えている加工・業務用野菜で、実需者から高い評価を得ている2社を紹介しよう。実需者ニーズに応じ効率的に生産するシステムを導入しサプライチェーンを築いている
【特集3】
- 野菜流通で存在意義高まる中間事業者
大泉 一貫
日本農業は、川上の商品企画、川中の農業者、川下の小売りなど販売のチェーンがつながっていないのではないか。チェーンの最適化に中間事業者の役割はいっそう増している
特別企画
- 令和農業の視点
こうして輸出を伸ばした
早くから海外市場を開拓してきた経営者たちの軌跡を知ろう。人口減少、ポストコロナ時代を生き抜く知恵が見えてくる
経営紹介
変革は人にあり
- 株式会社千葉ジェッツふなばし/千葉県
島田 慎二
肉用牛を1頭飼い、農畜産業をPRして支援。経営コンサルタントの経験を活かし、「苦しいときこそポジティブ」を信念に、激変する日本農業界を応援する
新・農業人
- 大地堂/滋賀県
廣瀬 敬一郎
競合することがない「古代小麦」の新市場を創る、という明確な経営戦略と熱い想いを持つ農業者。種の輸入、栽培技術の確立など、多くの困難を乗り越え経営を確立させていく
シリーズ・その他
観天望気
- 加工・業務用野菜の現場から 木村 幸雄 2
フォーラムエッセイ
- 甘くておいしい赤い実 緒川 たまき 24
主張・多論百出
- 株式会社ナチュラルアート 鈴木 誠 25
まちづくりむらづくり
- 千年伝承してきた暮らしのなか
心の通じる交流が新観光資源に
一般社団法人そらの郷/徳島県三好市
出尾 宏二 27
耳よりな話 219回
- 日本初の民間洋式牧場 加茂 幹男 30
書評
-
大竹 道茂 著
『江戸東京野菜の物語 伝統野菜でまちおこし』
青木 宏高 33
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者の皆さまへ 34
インフォメーション:農林水産省からのお知らせ
- 後継者不在の農業用ハウス
再整備・改修して後継者につなぐ支援が始まりました
農林水産省生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室 35 - 農業者と農林水産省をつなぐMAFFアプリ、使っていますか
農林水産省大臣官房政策課 36
みんなの広場・編集後記 37
TiDBit:上級農業経営アドバイザーのこぼれ話
- 設備投資のリスクと判断 久田 博司 38
9月号予告
- 特集は、「持続可能な水産業の課題」を予定。
魚介類の消費量や水産業の就業者数の減少など多くの課題を抱える水産業だが、持続可能な発展に向けさまざまな取り組みがおこなわれている。川上、川中、川下での課題を把握するとともに、水産業の可能性を実現する最新の取り組みを追う。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2020年6・7月合併号「自然資本の経済はじまる」
特集
短期集中3回連載「SDGs、その役割を問う」最終回
自然資本の経済はじまる
【特集1】
- 自然資本に配慮した持続可能な産業
藤田 香
自然資源を経営基盤ととらえ、持続可能に利用する「自然資本経営」がグローバルスタンダードとなりつつある。国内での取り組みは東京五輪を契機に加速し、地域活性化にもつながっている
【特集2】
- 環境への負荷の小さい農業を広げる
小野 邦彦
「環境保護」はSDGsの大きな柱の一つだ。環境保全に策を講じず利益のみ追求する農業から脱却しなければならない。持続可能な社会、環境の実現へ奮闘する農業者を紹介
【特集3】
- 水産エコラベルは産業と生活の架け橋
垣添 直也
水産資源の持続的利用や生態系の保全維持には資源管理活動が重要だ。海洋の自然環境や資源管理に配慮した水産物であることを示すためには、水産エコラベルの普及がかかせない
情報戦略レポート
- 新しく始まった収入保険制度への加入状況
―2020年1月調査―
経営紹介
新・農業人
- 大石 博/神奈川県
縁もゆかりもない土地で、農業の知識や経験をまったく持たずに就農した若手農業者。持ち前の行動力によって、いまでは次世代を担う若手農業者と期待されるまでになった
変革は人にあり
- 中森農産株式会社/埼玉県
中森 剛志
高齢化が進む日本の農業を支えようと、矢継ぎ早に農地を引き受け規模拡大。食料安保を担うべく、未来を見据えて世界水準の効率的な水田農業をめざす
シリーズ・その他
観天望気
- オーガニックは不可能じゃない 高橋 勉 2
農と食の邂逅
- 山田 奈緒/滋賀県 19
青山 浩子(文) 河野 千年(撮影)
フォーラムエッセイ
- おいしいひと皿 宮本 しばに 22
主張・多論百出
- グリーンカルチャー株式会社 金田 郷史 25
耳よりな話 218回
- 日本発の環境制御システム 吉岡 宏 30
まちづくりむらづくり
- 中山間農地を整備、集積
地域住民の協働のくらしを創る
農事組合法人福の里/山口県阿武町
市河 憲良 31
書評
-
稲垣 栄洋 著
『イネという不思議な植物』
宇根 豊 34
インフォメーション
- 第15回アグリフードEXPO東京2020 開催中止のお知らせ
情報企画部 35 - 金沢支店発
勉強会と交流会を開催しました 35
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者の皆さまへ 36
みんなの広場・編集後記 37
TiDBit:上級農業経営アドバイザーのこぼれ話
- 「八百屋の学問」を実践する 38
木山 雅人
8月号予告
- 特集は「変化する消費者ニーズに対応した野菜産地の方策とは」を予定。
経済・社会活動の転換期にあたり、野菜産地には大きく変化する消費者ニーズへの対応力が問われている。今後の生き残りに向けてカギを握る加工・業務用野菜への取り組みを踏まえ、野菜産地発展の方策を考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2020年5月号「多様な人材を生かす農業」
特集
短期集中3回連載「SDGs、その役割を問う」②
多様な人材を生かす農業
【特集1】
- 地域共生社会づくりにつながる農福連携
豊 輝久
農業と福祉の両サイドにメリットのある農福連携を推し進め、裾野を広げることは、SDGsの目標8に通じる。農福連携推進へ向けたわが国の取り組みとは
【特集2】
- シングルマザー移住が地域環境底上げ
山田 優
兵庫県神河町は、人口増大による地域おこしを狙った「シングルマザー移住支援事業」を、働く環境整備や子育て環境の底上げにもつなげている。現場をレポートしよう
【特集3】
- 農福連携は付加価値を生み癒し効果も
本誌編集部(特別取材班)
農業は人に優しく、すべての人に働く場をつくり出す。人手不足の農業と就労の場を求める福祉法人。お互いを支え合う農福連携の現場に、持続可能な社会のモデルを見た
情報戦略レポート
- 「簡便化」が「経済性」を初めて上回る食品の購入判断は7割が価格に集中
―消費者動向調査(2020年1月調査)―
経営紹介
新・農業人
- 株式会社FORTHEES/長崎県
福田 新也
海外での商談会の体験をヒントに、仲間とともに碾茶、抹茶加工に取り組み始めた茶農家3代目。市場に影響されない収益の柱に育てようと奮闘する
変革は人にあり
- 株式会社誠和/栃木県
大出 祐造
「農家の勘」を数値化し、ハウス栽培の環境制御システムを商品化。スマート農業や最先端技術の研究に取り組む他、コンサルティング会社も設立し、日本農業界に世界基準を示す
シリーズ・その他
観天望気
- 食育に学ぶこと アグネス・チャン 2
農と食の邂逅
- 地主 佳代子/三重県 19
青山 浩子(文) 河野 千年(撮影)
フォーラムエッセイ
- 今日のご褒美、明日の楽しみ 西村 元貴 22
主張・多論百出
- 一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所 藤山 浩 25
耳よりな話 217回
- ロボット農機を社会に届ける準備 杉本 光穗 30
まちづくりむらづくり
- 野菜の無人直売所や希少なキノコ栽培
大学生インターンシップ受け入れが刺激
藤沢活性化協議会/青森県平内町
森田 泰男 31
書評
-
竹下 大学 著
『日本の新種はすごい うまい植物をめぐる物語』
青木 宏高 34
インフォメーション
- 講演と討議を通じ林業界の課題を考える
九州地区総括課 35 - 大都市圏での店舗展開を柿農家が語る
奈良支店 35 - 農業分野の法務に目を向け同業者と交流する
高松支店 35 - 観光農園経営者から儲かる農業を学ぶ
甲府支店 35
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者の皆さまへ 36
みんなの広場・編集後記 37
TiDBit:上級農業経営アドバイザーのこぼれ話
- リスクを回避する視点が重要 38
池田 太
6月号予告
- 特集は、「環境に優しい持続可能な農林漁業~SDGsシリーズ~」を予定。
生産性の向上と効率化を追求した結果、工業化が進む農林漁業。今後は、環境への配慮といった社会性、地域性の観点が求められる。SDGsへの理解が進むなか、環境に優しい農林漁業経営の在り方を考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2020年4月号「「食品ロス」削減の潮流」
特集
短期集中3回連載「SDGs、その役割を問う」①
「食品ロス」削減の潮流
- いま、「食品ロス」が問いかけること
小林 富雄
食品ロスに向けた日本の取り組みは歴史が浅い。SDGsの精神にのっとり「食品ロス削減推進法」を推進するための未来図とは。海外各国の先進事例から考察する - 食料には「つくる責任」と「つかう責任」
ボリコ M.チャールズ
国際社会が食料と農業を考える上で、食料のロスと廃棄の問題を避けることはできない。先進国では廃棄が大きな問題で、製造者だけでなく消費者にも責任がある - 廃棄物発生抑制に果敢に挑む企業、地域
井出 留美
真のSDGsへ対応するとは、SDGsウォッシュではなく3Rの最優先であるリデュースに集中し、経済性のみならず持続可能を担保することだ。先進的な取り組みを紹介しよう
情報戦略レポート
- 耕種・畜産とも売上高横ばい
費用増で多くの業種で減益
―2018年農業経営動向分析(法人経営)―
経営紹介
経営紹介
- 新・農業人
株式会社ベストシーン/和歌山県
鈴木 崇文
2017年、20年勤めた会社を退職し起業。農業参入した当初より「付加価値ある加工品」で勝負をしたいと考え、選択したのは「甘酒」だ
変革は人にあり
- 株式会社セントラルフルーツ/京都府
田中 勝三
八百屋のイメージを覆すスタイリッシュな売り場づくりで「潜在購買力」を発掘。惣菜店や農業部門にも進出し、農業・流通・食の3事業がそろう100年企業をめざす
シリーズ・その他
観天望気
- マインドの時代 山田 敏之 2
農と食の邂逅
- 吉原 サラ/岡山県 19
青山 浩子(文) 河野 千年(撮影)
フォーラムエッセイ
- 美味しい信州 山本 麗子 22
主張・多論百出
- しずおかコンシェルジュ株式会社 海野 裕子 25
耳よりな話 216回
- パスタの品質を表す言葉 早川 文代 30
まちづくりむらづくり
- 農業経営者を育てる「SEADS」
鶴岡から全国へ、就農者募り開校
鶴岡市役所/山形県鶴岡市
髙橋 和博 31
書評
-
田中 信一郎 著
『政権交代が必要なのは、総理が嫌いだからじゃない』
武本 俊彦 34
インフォメーション
- オホーツクで学ぶ学生と地元での就農を考える
北見支店 35 - 事業計画の作成手法を学び経営を考えるワークショップ
岡山支店 35 - データ収集と分析に基づく分かりやすい助言のコツ
神戸支店 35 - 地元のレアな農産品を実需者につなぐ機会を提供
長野支店 35 - 台湾で商談会開催 初めての輸出を後押し
情報企画部 36
編集後記 37
TiDBit:上級農業経営アドバイザーのこぼれ話
- 牛舎に行かないコンサル 38
井﨑 敏彦
5月号予告
- 特集は、SDGsシリーズ第2弾「あらゆる人々が活躍する社会へ」を予定。
SDGsによる持続可能な共生社会の実現に向け、政府では一億総活躍社会を掲げる。農林水産分野においても、農福連携の取り組みや、女性活躍のプロジェクトが進む中、活躍が期待される多様な人材について、今後の可能性、支援の在り方を考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2020年3月号「酪農経営最前線:NOW」
特集
酪農経営最前線:NOW
- メガロボットファーム化進む北海道酪農
斉藤 裕基
最先端のロボットやICT導入により生産基盤の維持・拡大を続けてきた北海道の酪農。さらなる生乳生産量拡大のためには、輸入乳製品への対抗策が急務である - 先細りの都府県酪農、復活の糸口とは
細井 洋行
都府県における酪農では、生乳生産量が右肩下がりの状況が続いている。その中にあって業績を伸ばす湯田牛乳公社の取り組みから、都府県酪農の生き残り策を考える - カッコイイ酪農へ、スマート農業の挑戦
菱沼 竜男
次世代閉鎖型搾乳牛舎、ロボット搾乳など最新技術を取り入れることで労働環境を改善しようと実証試験がなされている。従来のイメージを覆す次世代酪農の姿とは
情報戦略レポート
- 耕種・畜産とも売上高は横ばい
収益は費用増で減益
―2018年農業経営動向分析(個人経営)―
経営紹介
経営紹介
- 有限会社アグリプラント/山口県
福永 彰
流行をいち早くキャッチしニッチ野菜を生産、食べ方を発信することで販路を開拓し現在では国内有数の生産量を誇る。成功の秘訣は需要に必ず応えることだと語る
変革は人にあり
- 株式会社アジチファーム/福井県
伊藤 武範
情報コンサル出身者が農業生産法人を継承した。駐越経験を活かし、日本でベトナム米、ベトナムで日本米を栽培する事業に取り組み拡大を続ける。
シリーズ・その他
観天望気
- 家族酪農の発信力 鵜川 洋樹 2
農と食の邂逅
- 丸尾 美香/兵庫県 19
青山 浩子(文) 河野 千年(撮影)
フォーラムエッセイ
- 忘れられない牛乳の味 草刈 正雄 22
主張・多論百出
- 株式会社ファームステッド代表取締役 長岡 淳一 25
耳よりな話 215回
- 技術革新著しい搾乳機械 加茂 幹男 30
まちづくりむらづくり
- 中学生が地域おこしに会社を設立
目標は100年スパンのまちづくり
株式会社氷川のぎろっちょ/熊日宮原販売センター
熊本県八代郡氷川町
岩本 剛 31
書評
-
丸山 俊一+NHK「欲望の時代の哲学」制作班 著
『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学する』
宇根 豊 34
インフォメーション
- 千葉ジェッツに学ぶ経営を強くするノウハウ
千葉支店 35 - 林業の専門家が語る里山や木材利用の可能性
近畿地区総括課 35 - 異業種からの農業参入を実例から学ぶ
富山支店 35 - 雇用問題や地域課題に農業経営が貢献できること
北見支店 35
資金紹介 36
みんなの広場・編集後記 37
ご案内
- 第15回アグリフードEXPO東京2020 38
4月号予告
- 特集は、「食品ロス削減の潮流から学ぶ~SDGsシリーズ~」を予定。
SDGsと農林水産業・食品産業とのかかわり合い、中でも2030年度に2000年度の半減を目標とする食品廃棄物(食品ロス)問題について、諸外国における取り組み事例から国内での取り組みの在り方について考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2020年2月号「国産材促進の方策を追う」
特集
国産材促進の方策を追う
- みんなで取り組むウッド・チェンジ
長野 麻子
国産材の利用増大のためには、公共建築物など非住宅建築物の木質化が重要だ。「伐って使って植える」持続可能なサイクルをつくり、森林資源の循環的利用をはかることが課題である - 国産材の需要をひらく新たな挑戦
高田 克彦、佐々木 貴信
橋梁、治山・治水施設など土木分野でも国産材の利活用が進み、高度化している。さらなる利活用を図るためには、乗り越えるべき3つの課題がある - CLT集成材の活用が国産材を復活
佐々木 幸久
国産材需要の半数を占める住宅建築は、人口減少により需要減退が予想される。新たな需要創出に、大断面集成材やCLTは木造建築の可能性を高めることができる
情報戦略レポート
- 5年前に比べ女性の雇用割合が増加
景況感、改善するも低迷抜けず
―農業景況調査(2019年7月調査)―
経営紹介
経営紹介
- Bioフォレステーション株式会社/神奈川県
近藤 亮介
スケールメリットを追求し林齢の平均化された山林に整える。強みの燃料用チップで利益を確保しつつ、未来を見据えた経営戦略を展開する
変革は人にあり
- 日髙勝三郎商店/宮崎県
日髙 勝三郎
90年続く素材生産業者の三代目。伐採と造材に加えて再造林も手掛け、森林環境保全に取り組むなど、丸太生産のプロ集団として責任ある森林経営をめざしている
シリーズ・その他
観天望気
- 木を見て、森も見て 寺岡 行雄 2
農と食の邂逅
- 尾池 美和/香川県 19
青山 浩子(文) 河野 千年(撮影)
フォーラムエッセイ
- 真冬の雪のなかにも 平松 洋子 22
主張・多論百出
- 森林ジャーナリスト 田中 淳夫 25
耳よりな話 214回
- 中国の食糧難を救ったマルチ栽培 吉岡 宏 30
まちづくりむらづくり
- 地場産そば粉100%のそば屋が人気
互助と信頼で結ばれた集落が取り組む
有限会社荒神の里・笠そば/奈良県桜井市
山本 信廣 31
書評
-
藤井 一至 著
『土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて』
青木 宏高 34
インフォメーション
- オープンイノベーションで創り出す
新しい林業ビジネス
林野庁 森林整備部 整備課 造林間伐対策室 35
みんなの広場・編集後記 37
ご案内
- 第13回アグリフードEXPO大阪2020 38
3月号予告
- 特集は、「酪農経営の最前線を追う」を予定。
酪農は他業種と比較し労働時間が長いという課題を抱え、全国ベースの乳用牛飼養戸数、生乳生産量は右肩下がりの状況にある。酪農の生産基盤を強化し、生乳生産量を維持・拡大するためのカギは何か。酪農経営の次なるステージを見据え、業界の最前線を追う。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2020年1月号「食育。次世代への有り様」
特集
食育。次世代への有り様
- 先進的な食育に取り組む鯖江市の実践
帰山 順子
全国に先駆け、市を挙げて食育に取り組む福井県鯖江市。「医食同源」に地域農業を取り込んだ「医食農同源」をテーマにさまざまな活動を繰り広げ、生涯を通じた食育をめざす - 新しい生活者に寄り添う食育とは
太田 恵理子
最新の調査から食に関する意識や行動を分析。全世代で食生活の変化が進む中、若年層では『食の共有』『外部活用』という二つのオピニオンリーダーが育っている - いま待ったなしに食育と食農教育
上岡 美保
日本農業を守り食料自給率を上げるには地産地消、国産国消が欠かせない。意識改革には次世代への食育や食農教育が必須であり、特に食育では学校給食が有効な手段だ
特別企画
- 令和元年度アグリフードEXPO輝く経営大賞
~駆け上がる地域農業の担い手たち~
有限会社舟形マッシュルーム/山形県
- 新春座談会♥『農と食の邂逅』
脇役から主役へ
女性農業が、離陸した
女性農業者が農業、農村に新風を吹かせる。農業には可能性しかないとはっきり言う3人が農業の展望を語る
経営紹介
経営紹介
- 堀養蜂園/岐阜県
堀 孝之
養蜂を始め、わずか5年で当初計画の2倍の売り上げを達成した。ストーリーブランディングを重視し、東濃の自然環境だからこそ作れる蜂蜜を催事などで直販する
変革は人にあり
- 有限会社藤井牧場/北海道
藤井 雄一郎
乳牛1000頭を誇る大規模農場を経営。牛舎の砂床導入や農場HACCP認証取得、さらには生乳の品質向上に取り組むなど、進取の気性に富む酪農家に迫る
シリーズ・その他
観天望気
- 東京2020大会と「食」の持続可能性 松本 恵 2
フォーラムエッセイ
- 食べること、生きること 中江 有里 30
まちづくりむらづくり
- 集荷がもたらすヒトとモノの往来
中山間地域の生産者に便宜供与
JAおおいた「オアシス春夏秋冬」/大分県中津市
岡本 真徳 31
耳よりな話 213回
- 鳥インフルエンザと水辺の関係 清水 友美子 34
書評
- 京都大学経済研究所附属先端政策分析研究センター 編
『政策をみる眼をやしなう』
武本 俊彦 35
インフォメーション
- 持続可能な農林水産業を見据え公庫に期待すること
情報企画部 36 - 広域ネットワークを活かした展示商談会を開催
東北6県の日本公庫各支店 36 - 女性・高齢者・農福連携など人材活用をテーマに講演
近畿地区総括課 36 - 県内新規就農者同士のネットワークづくりを支援
奈良支店 36
みんなの広場・編集後記 37
ご案内
- 第13回アグリフードEXPO大阪2020 38
2月号予告
- 特集は、「国産材利用促進へ向けた需要創造策とは」を予定。
戦後まもなく定植された人工林が伐期を迎える中、少子化などの影響で住宅着工戸数は伸び悩み、新たな需要創造が求められている。木材需要の中で大きなウエートを占める建築用材における効果的な対策は何か。事例を踏まえ考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。