2024年の発行号一覧
2024年秋2号「働き手を補う農業サービス」
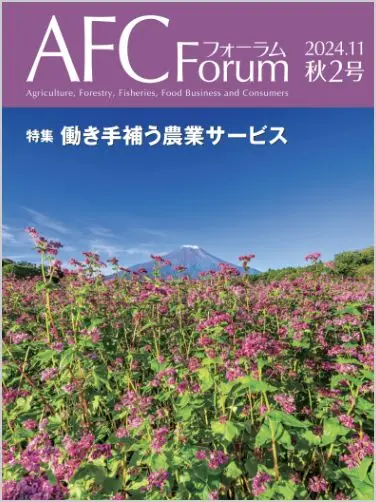
-
-
特集巻頭言
- 観天望気
- 多様化するニーズと採用戦略
横山 拓哉/株式会社マイナビ 地域活性CSV事業部 事業部長
- 多様化するニーズと採用戦略
経営紹介レポート- 調査レポート
- 2024年上半期農業景況DIは
やや改善するもマイナス値が継続──農業景況調査(2024年7月調査)──
- 2024年上半期農業景況DIは
連載- フォーラムエッセイ
- 迫りくる食料不足と戦う
山中 基/株式会社ゴールデンウルヴス福岡 代表取締役
- 迫りくる食料不足と戦う
- 主張・多論百出
- 地域経済の活性化にも効果大きい
短期労働力確保に向けた課題とは髙木 英彰/一般社団法人JA共済総合研究所
- 地域経済の活性化にも効果大きい
- ぶらり食探訪 ―プサン―
- 日本産水産物の需要と魅力発信
米窪 紫帆/在釜山日本国総領事館 領事
- 日本産水産物の需要と魅力発信
- 耳よりな話 第257回
- 女性従業員の定着へ 男女別トイレ設置のススメ
澤野 久美/国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- 女性従業員の定着へ 男女別トイレ設置のススメ
- 地域再生への助走
- 外国人の働き手を産地間でリレー
嬬恋村と宮崎県、人材会社が連携長友 宏諭/一般社団法人宮崎県農業法人経営者協会 事務局
橋詰 元良/嬬恋キャベツ振興事業協同組合 事務局
下條 優樹/株式会社ウイルテック 海外事業企画部
- 外国人の働き手を産地間でリレー
インフォメーション- 災害のお見舞い
- 編集後記
農業経営アドバイザー- TiDBit
- 日本の将来 北海道の将来の為に
農業を支援します薄井 タカ子/税理士法人薄井会計
- 日本の将来 北海道の将来の為に
次号予告- 冬1号(1月発行)
「日本産酒類のさらなる輸出拡大に向けて(仮)」- アルコール飲料(日本産酒類)の輸出額は10年前に比べ5倍以上に拡大した。外国人のニーズをつかんだ日本独自の生産や販売とは何か。地域の酒造会社の輸出戦略と課題解決に向けた国の施策を通じて、日本産酒類輸出の現状と今後の展望を考える。
表紙説明撮影:縄手 英樹
*本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
山梨県山中湖村
2023年10月6日
赤ソバの花
■秋晴れの日、赤ソバの濃いピンク色の花が畑一面に咲き誇る■
帯の色:杜若色 - 観天望気
-
2024年秋1号「水産資源管理の成果問う」
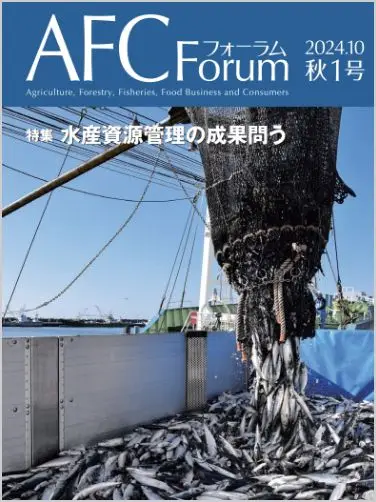
-
-
特集巻頭言
- 観天望気
- ミスマッチの解消
加藤 久雄/一般社団法人 全国まき網漁業協会 副会長理事
- ミスマッチの解消
経営紹介レポート- 調査レポート
- 物価上昇続き「経済性志向」
3半期連続で40%超え──消費者動向調査(2024年7月調査)──
- 物価上昇続き「経済性志向」
連載- フォーラムエッセイ
- 旬は寝て待て
野上 優佳子/料理家・弁当コンサルタント
- 旬は寝て待て
- 主張・多論百出
- 資源管理の新たなロードマップを策定
明るい未来に向け持続的利用を推進赤塚 祐史朗/水産庁資源管理部管理調整課 資源管理推進室 室長
- 資源管理の新たなロードマップを策定
- ぶらり食探訪 ―ドバイ―
- さらなる日本食品進出のカギとは
都甲 茉弥/ドバイ日本国総領事館 副領事
- さらなる日本食品進出のカギとは
- 耳よりな話 第256回
- 画像解析技術の資源研究への活用
山崎 いづみ/国立研究開発法人水産研究・教育機構
- 画像解析技術の資源研究への活用
- 地域再生への助走
- アジフライで地域創生めざす
知名度向上で市民の誇り醸成友田 吉泰/松浦市長
- アジフライで地域創生めざす
- 書評
- 『新さかなの経済学 漁業のアポリア』
石井 勇人/共同通信アグリラボ 編集長・宮城大学 特任教授
- 『新さかなの経済学 漁業のアポリア』
インフォメーション- みんなの広場
- 編集後記
農業経営アドバイザー- TiDBit
- 成功のカギは「やめない限り失敗ではない」
佐藤 正之/株式会社野村総合研究所
- 成功のカギは「やめない限り失敗ではない」
次号予告- 秋2号(11月発行)
「農業支援サービスを生かした労働力確保(仮)」- 農業の現場での人手不足が強まるなか、民間の農業支援サービスが動き出している。労働力を必要とする現場に人材派遣などをおこなう農業支援サービスに着目し、サービスの現状と課題、そしてさらなる成長や発展の可能性を考える。
表紙説明撮影:株式会社みなと山口合同新聞社
*本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
まき網によるサバの水揚げ
帯の色:コバルトブルー - 観天望気
-
2024年夏2号「2024年問題と農産品物流」

-
-
特集
- 2024年問題と農産品物流
農林水産業に「物流の2024年問題」が重くのしかかっている。ドライバー不足でトラックの輸送力が低下し、鮮度保持や長距離輸送の農水産物が影響を受けると見られる。解決策としてトラック輸送の効率化や中継輸送、共同物流、モーダルシフトが打ち出されるなど、農水産物輸送は見直しを迫られている。
- 業界全体で協調し持続可能な物流へ
原田 昌彦/三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 政策研究事業本部 経済財政政策部 主席研究員
- ストックポイントによる物流改善への取り組み
吉田 忠則/日本経済新聞社 編集委員
- モーダルシフト推進へ向け各社が模索
金子 弘道/ジャーナリスト
- 業界全体で協調し持続可能な物流へ
巻頭言- 観天望気
- 持続可能な物流へ、やればできる!
大島 弘明/流通経済大学 流通情報学部 教授
- 持続可能な物流へ、やればできる!
経営紹介連載- フォーラムエッセイ
- 食の循環、未来へのバトン
三國 清三/フランス料理シェフ
- 食の循環、未来へのバトン
- 主張・多論百出
- 最適な物流構築に共同化や連携が有効
卸売市場の活用も効率化に大きく貢献江口 慎一/株式会社轍 代表取締役
- 最適な物流構築に共同化や連携が有効
- ぶらり食探訪 ―シドニー―
- 「イナリ」「ワギュウ」は現地語化
高橋 浩之/時事通信社 シドニー支局
- 「イナリ」「ワギュウ」は現地語化
- 耳よりな話 第255回
- 野菜生育の「見える化」と収量予測技術
礒﨑 真英/国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- 野菜生育の「見える化」と収量予測技術
- 地域再生への助走
- オール愛媛で挑む2024年問題
トラック輸送の効率性向上を促す徳丸 淳哉、和田 大祐、三堂 博昭、大西 論平/愛媛県
- オール愛媛で挑む2024年問題
- 書評
- 『日本の物流問題 ――流通の危機と進化を読みとく』
吉田 忠則/日本経済新聞社 編集委員
- 『日本の物流問題 ――流通の危機と進化を読みとく』
インフォメーション- 災害のお見舞い
- 編集後記
農業経営アドバイザー- TiDBit
- 苦境に陥った農業者支援で意識していること
内田 勇介/税理士法人TAP
- 苦境に陥った農業者支援で意識していること
次号予告- 秋1号(10月発行)
「水産基本法改正と資源管理の今」- 水産基本法の改正から3年。水産庁は漁獲量の回復をめざして資源管理システムを導入しているが、魚種や地域間の乖離が大きく、成果はまだら模様だ。TACやIQ設定、資源評価など資源管理の現状を踏まえ、持続可能な漁業経営のあり方を考える。
表紙説明撮影:佐藤 尚
*本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
たわわに実る稲穂と八海山
■魚沼の里の田んぼが黄金色に染まり、稲穂がこうべを垂れる■
帯の色:菜の花色 - 2024年問題と農産品物流
-
2024年夏1号「異業種が見出す農の価値」

-
-
特集巻頭言
- 観天望気
- 農林水産業と風の時代
遠山 正道/株式会社スマイルズ 代表
- 農林水産業と風の時代
経営紹介レポート- 調査レポート
- 23年設備投資は7割超が実施
実施内容は「効率化」が最多──農業景況調査(2024年1月調査)──
- 23年設備投資は7割超が実施
連載- フォーラムエッセイ
- みんなを笑顔にするアイス
松本 薫/元柔道家
- みんなを笑顔にするアイス
- 主張・多論百出
- 地域課題解決に農山漁村発イノベーション
多様な考えを取り込み新たな価値の創出へ影山 義人/前 農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課長
- 地域課題解決に農山漁村発イノベーション
- ぶらり食探訪 ―台北―
- 台湾市場の開拓に必要なこと
野田 広宣/日本台湾交流協会 台北事務所 主任
- 台湾市場の開拓に必要なこと
- 耳よりな話 第254回
- 荒廃農地の再生とスマート放牧
渡辺 也恭/国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- 荒廃農地の再生とスマート放牧
- 地域再生への助走
- 生産者と消費者をつなぐ農園
地域と共存共栄し未来を創る井上 真梨子・敬二朗/稲作本店
- 生産者と消費者をつなぐ農園
- 書評
- 『湖池屋の流儀 老舗を再生させたブランディング戦略』
金子 弘道/ジャーナリスト
- 『湖池屋の流儀 老舗を再生させたブランディング戦略』
インフォメーション- みんなの広場
- 編集後記
- 次号予告
- 第17回アグリフードEXPO東京2024開催のご案内
次号予告- 夏2号(9月発行)
「農畜産物の『物流2024年問題』を追う(仮)」- 農畜産物の輸送は、商品の形状や量をそろえにくい、鮮度維持などの品質管理が厳しい、といった特徴がある。2024年4月以降「物流2024年問題」に直面するなか、物流の安定化・効率化に取り組む事業者の動きを追い、今後の農畜産物物流の持続可能性を探る。
表紙説明撮影:木崎 実
*本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
埼玉県秩父市
2019年6月22日
輝くプラムの実
■澄み切った青空の下、赤く色づいたプラムの実が風に揺れる■
帯の色:蘇枋色 - 観天望気
-
2024年春2号「国産調達へ動く食品企業」
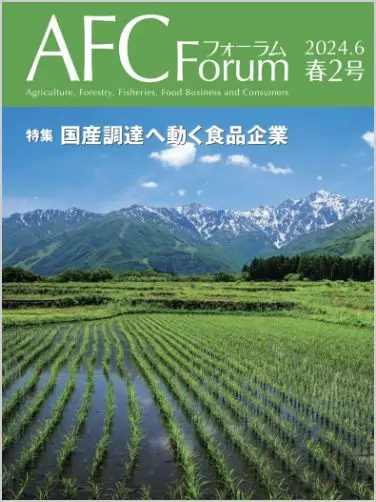
-
-
特集巻頭言
- 観天望気
- 価格は誰が決めるのか
荒川 隆/一般財団法人食品産業センター 理事長
- 価格は誰が決めるのか
経営紹介レポート- 調査レポート
- 農業景況DIはマイナス幅縮小
食品産業の景況は全業種でプラス──農業景況調査・食品産業動向調査(いずれも2024年1月調査)──
- 農業景況DIはマイナス幅縮小
連載- フォーラムエッセイ
- スープの旅と洗い里芋
有賀 薫/スープ作家
- スープの旅と洗い里芋
- 主張・多論百出
- 食の外部化とともに注目高まる原産地表示
食品事業者と産地の連携で国内自給向上へ清水 みゆき/日本大学生物資源科学部 教授
- 食の外部化とともに注目高まる原産地表示
- ぶらり食探訪 ―ニューデリー―
- 日本産品の浸透と輸入規制
植木 啓太/時事通信社 ニューデリー支局
- 日本産品の浸透と輸入規制
- 耳よりな話 第253回
- 天敵を利用した果樹のハダニ管理
外山 晶敏/国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- 天敵を利用した果樹のハダニ管理
- 地域再生への助走
- 町の資源であるコメを最大限活用
官民一体となり地域の発展に貢献菅野 剛/株式会社加悦ファーマーズライス
- 町の資源であるコメを最大限活用
- 書評
- 『Foodscape フードスケープ 図解 食がつくる建築と風景』
石井 勇人/共同通信アグリラボ 編集長・宮城大学特任教授
- 『Foodscape フードスケープ 図解 食がつくる建築と風景』
インフォメーション- みんなの広場
- 編集後記
- 次号予告
- 第17回アグリフードEXPO東京2024開催のご案内
次号予告- 夏1号(8月発行)
「異業種の視点が農林漁業を変える(仮)」- 経営環境の変化が著しい農林漁業。原料調達先や販売先の変更を余儀なくされるなか、異業種の視点から農林漁業を見つめ、課題解決につなげているケースがある。異業種連携による付加価値創造を通じた、持続可能な農林漁業経営への道筋を探る。
表紙説明撮影:館野 二朗
*本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
長野県白馬村
2013年6月4日
水田と白馬連峰
■雪の残る白馬連峰。麓の田んぼでは若い稲が元気よく伸びる■
帯の色:パロットグリーン - 観天望気
-
2024年春1号「農の成長、金融への期待」

-
-
特集巻頭言
- 観天望気
- 地域連携が未来を創る
川田 淳次/農林中央金庫 常務執行役員
- 地域連携が未来を創る
経営紹介レポート- 調査レポート
- 「健康志向」と「簡便化志向」上昇 「経済性志向」も40%超えを維持
──消費者動向調査(2024年1月調査)──
- 「健康志向」と「簡便化志向」上昇 「経済性志向」も40%超えを維持
連載- フォーラムエッセイ
- 食は第二の母
金田 朋子/声優
- 食は第二の母
- 主張・多論百出
- 経営存続の鍵は資金繰りの維持
金融機関に求められる継続支援森 佳子/島根大学生物資源科学部農林生産学科 准教授
- 経営存続の鍵は資金繰りの維持
- ぶらり食探訪 ―ダイデスハイム―
- 和食とドイツワインのペアリング
山本 拓也/時事通信社ベルリン支局
- 和食とドイツワインのペアリング
- 耳よりな話 第252回
- ゼロエミッション農業をめざす
須藤 重人/国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- ゼロエミッション農業をめざす
- 地域再生への助走
- 地域金融機関としての役割
栃木県の農業を支え続ける金田 和久/栃木銀行 法人営業部
- 地域金融機関としての役割
- 書評
- 『百姓の遺言』
吉田 忠則/日本経済新聞社 編集委員
- 『百姓の遺言』
インフォメーション- 災害のお見舞い
- 編集後記
- 次号予告
- 第17回アグリフードEXPO東京2024開催のご案内
次号予告- 春2号(6月発行)
「食品産業の国産原材料への調達転換の動き(仮)」- 地政学リスクの増加や世界的な食料需給のひっ迫感が続くなか、食品メーカーの原材料の国産化への動きが加速している。生産者から加工・流通事業者まで、わが国の農業の6次産業化に向けた農商工連携の動きを通して、食料の安定供給の確保と食料自給率の向上に関する課題と展望を探る。
表紙説明撮影:縄手 英樹
*本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
佐賀県嬉野市
2023年3月28日
百年桜と茶畑
■雲一つない青空の下、満開の桜と茶畑のコントラストが美しい■
帯の色:コスモス色 - 観天望気
-
2024年冬2号「スギから読む新しい林業」
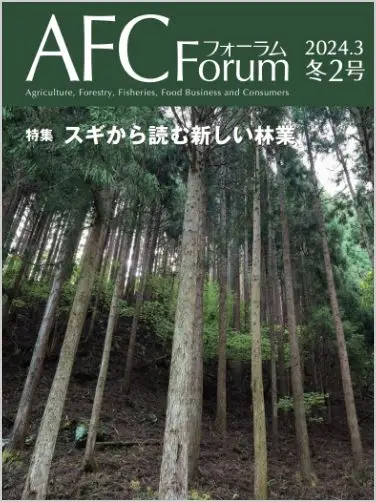
-
-
特集巻頭言
- 観天望気
- スギの山元立木価格と木造ビル
青山 豊久/林野庁 長官
- スギの山元立木価格と木造ビル
経営紹介レポート- 調査レポート
- 2022年も多くの業種で経費が増加
──2022年農業経営動向分析──
- 2022年も多くの業種で経費が増加
連載- フォーラムエッセイ
- 日本の森を旅する
姉崎 一馬/自然写真家・絵本作家
- 日本の森を旅する
- 主張・多論百出
- カーボンニュートラル社会の実現に向けて
需要と規模を見極め戦略的に木材輸出促進立花 敏/筑波大学 生命環境系 准教授
- カーボンニュートラル社会の実現に向けて
- ぶらり食探訪 ―ロンドン―
- カフェから見える日本産抹茶事情
磯部 敦子/時事通信社 ロンドン支局
- カフェから見える日本産抹茶事情
- 耳よりな話 第251回
- スギ花粉の飛散を防止する技術
髙橋 由紀子/国立研究開発法人森林研究・整備機構
- スギ花粉の飛散を防止する技術
- 地域再生への助走
- 町独自の研修制度で担い手の育成・確保
官民一体で林業成長産業化地域をめざす奥田 誠/高知県仁淀川町 農林課
- 町独自の研修制度で担い手の育成・確保
- 書評
- 『全部、山が教えてくれた
─林業のこれから─ 改訂版』金子 弘道/ジャーナリスト
- 『全部、山が教えてくれた
インフォメーション- 災害のお見舞い
- 編集後記
- 次号予告
農業経営アドバイザー- TiDBit
- 農業経営者の「農力」向上のため力を尽くす
大久保 荘司/税理士法人のぞみ
- 農業経営者の「農力」向上のため力を尽くす
次号予告- 春1号(4月発行)
「地域金融機関の農業融資への取組み(仮)」- 日本公庫や農協などが中心だった農業金融に、地域金融機関が相次ぎ参入している。地域商社の設立やコンサルティングなど農業金融の現状と課題を追い、地域金融機関が担う農業経営の成長産業化への可能性を探る。
表紙説明撮影:山梨 勝弘
*本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
鳥取県智頭町
2016年5月7日
朝の杉林
■まっすぐと天に向かい伸びる杉林の間から朝の光が差し込む■
帯の色:千歳緑 - 観天望気
-
2024年冬1号「地域をつくる資源の価値」

-
-
特集巻頭言
- 観天望気
- 支持される理由
藻谷 浩介/株式会社日本総合研究所 主席研究員
- 支持される理由
経営紹介レポート- 調査レポート
- 食品産業の景況は6年ぶりにプラス
輸出の取り組み意欲も上昇──食品産業動向調査(2023年7月調査)──
- 食品産業の景況は6年ぶりにプラス
連載- フォーラムエッセイ
- 日本は個性豊かな食の宝庫
伊藤 聡子/フリーキャスター
- 日本は個性豊かな食の宝庫
- 主張・多論百出
- 「守る」から「稼ぐ」へ発想を転換
農林水産分野の知的財産を活用する松本 修一/農林水産省 知的財産課
- 「守る」から「稼ぐ」へ発想を転換
- ぶらり食探訪 ―ニューヨーク―
- コメとホタテと食料安保
山田 司/時事通信社 ニューヨーク総局
- コメとホタテと食料安保
- 耳よりな話 第250回
- 環境にやさしい土壌消毒技術
根角 厚司/農業・食品産業技術総合研究機構
- 環境にやさしい土壌消毒技術
- 地域再生への助走
- 地域の特色を生かした地鶏を生産
各種認証取得し地域活性化に貢献辻 貴博/阿波尾鶏ブランド確立対策協議会
- 地域の特色を生かした地鶏を生産
- 書評
- 『葬儀会社が農業を始めたら、サステナブルな新しいビジネスモデルができた』
石井 勇人/共同通信アグリラボ 編集長
- 『葬儀会社が農業を始めたら、サステナブルな新しいビジネスモデルができた』
インフォメーション- みんなの広場
- 編集後記
- 次号予告
農業経営アドバイザー- TiDBit
- 事業者と共に解決策を探る良き相談相手に
原口 勝全/原口経営コンサルタントオフィス
- 事業者と共に解決策を探る良き相談相手に
次号予告- 冬2号(3月発行)
「スギから見通す林業の未来」- 国がめざす「伐って、使って、植えて、育てる」森林の循環利用には国産材の需要拡大、国産材の価格競争力向上、林業経営のコスト低減が欠かせない。国内人工林の4割を占める、スギを通して林業の現状と持続可能な未来を考える。
表紙説明撮影:萩原 俊哉
*本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
群馬県吾妻郡嬬恋村
2013年1月1日
キャベツ畑と浅間山の朝
■噴煙を上げる浅間山の麓、畑に積もった新雪を朝日が照らす■
帯の色:銀色 - 観天望気
-