- ホーム
- 刊行物・調査結果
- 農林水産事業 AFCフォーラム、アグリフードサポート、情報戦略レポート
- 農林水産事業 AFCフォーラム(2023年)
農林水産事業 AFCフォーラム(2023年)
2023年秋2号「成長産業へ養殖業の模索」
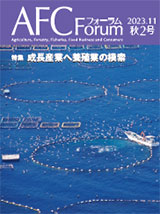
-
電子ブック版(82.9MB)
特集
成長産業へ養殖業の模索
【特集】
- 養殖業の成長産業化に向けた道筋とは
柿沼 忠秋/水産庁 増殖推進部 栽培養殖課長
日本における養殖業の割合は少しずつ伸びている。どうすれば養殖業が成長産業になれるのか、水産庁が取り組みを解説する
- 養殖業がもたらす市場開拓と地域振興
金子 弘道/ジャーナリスト
生産者主導のバリューチェーン構築により世界をめざす養殖と、地域一体となった地産地消型の養殖。異なる路線を進む二つの事例
巻頭言
観天望気
- 豊かな海とともに進化する
田中 輝/ 株式会社ニッスイ 執行役員 水産事業副執行・養殖事業推進部管掌
連載
変革は人にあり
- 小濵 秀則/ 株式会社小浜水産グループ(鹿児島県)
飼料コストの削減と品質の向上を同時に実現する独自の給餌方法「オバマスタイル」。その開発秘話や販売戦略を聞いた
農と食の邂逅
- 深川 沙央里/ 株式会社クリエーションWEB PLANNING(熊本県)
網元の家に生まれ、父の叱咤激励を受け水産業に邁進。クルマエビ販売会社を設立後、個人としても養殖事業をおこなう
新・漁業人
- 門林 一人/株式会社門林水産(広島県)
「通し替え」などカキ養殖関連業から、カキ養殖業、種苗販売業にも乗り出す。全国の生産地を結ぶ協会も設立し、カキ生産業を次代へつなぐべく行動する
オピニオン・レポート
フォーラムエッセイ
- 基本はアジ
長谷川 弓子/料理家
調査レポート
- 農業景況DIはマイナス値が継続 生産コスト高で今後も厳しい見通し
─農業景況調査(2023年7月調査)─
主張・多論百出
- 大規模な閉鎖型の陸上養殖が日本進出
海洋汚染や病気をなくし世界に普及へ
エロル・エメド/ソウルオブジャパン株式会社 代表取締役社長
ぶらり食探訪 ―バンコク―
- 食生活支える屋台とデリバリー
松尾 紘子/国連環境計画(UNEP) アジア太平洋地域事務所
耳よりな話 第249回
- 卵を産ませる養殖技術
入路 光雄/水産研究・教育機構
地域再生への助走
- 低・未利用資源の組み合わせ
「キャベツウニ」開発と広がり
臼井 一茂/神奈川県水産技術センター 企画研究部(神奈川県)
書評
- 『魚ビジネス ――食べるのが好きな人から専門家まで楽しく読める魚の教養』
吉田 忠則/日本経済新聞社 編集委員
インフォメーション
- 先輩農業者の話を聞く 千葉支店
- ドバイへの輸出事例を学ぶ 秋田支店
- 漁業者のための事業承継セミナー 水戸支店
- J-クレジットの勉強会 大分支店
- 長崎公庫水産友の会 長崎支店
- 生産者が地元食材を売り込む 盛岡支店
- 日本公庫電子契約サービスのご案内 融資企画部
- みんなの広場・編集後記
農業経営アドバイザー
TiDBit
- 生産者と共にわくわくできる組織をめざす
中島 英利/株式会社HAL GREEN代表取締役
次号予告
- 次号の特集は、「資源活用(人材・特産品)による地域の活性化戦略」を予定。今後、さらなる人口減少が見込まれるなか、中長期的に生産基盤を維持し地域活性化を図るには、人材の育成・確保や、地域の特産品に付加価値を付け発信していくことが必要だ。農業参入による遊休農地の再生や雇用の創出、地理的表示(GI)の活用などの事例を交えて考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
撮影:田中 正秋
高知県幡多郡大月町 柏島
2013年3月30日
柏島の養殖いけす
■クロマグロの養殖。海に浮かぶいけすは幾何学模様のようだ■
帯の色:桔梗色
2023年秋1号「地域色生かした農地活用」
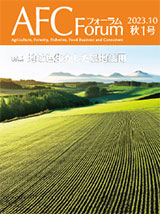
-
電子ブック版(80.5MB)
特集
地域色生かした農地活用
【特集】
- 地域の特色ある産地形成を推進
梅下 幸弘/農林水産省 農産局 企画課 水田農業対策室長
農林水産省は水田の畑地転換などの施策を整え、農地活用を促している。魅力ある産地づくりには地域での検討が求められる
- 大規模経営から見る農地保全戦略
吉田 忠則/日本経済新聞社 編集委員
農地を守ることは日本の食料安全保障に直結する。農業を取り巻く課題が山積するなか、農地をどう維持し、活用していくのか。二つの事例から考察する
巻頭言
観天望気
- 日本の農地が拓く未来
齋藤 一志/日本農業法人協会 会長
連載
変革は人にあり
- 井狩 篤士/株式会社イカリファーム(滋賀県)
需要が拡大する小麦の生産を従来の米に代わる経営の柱に据える。学校給食や有力コンビニなど大口実需者を捉えながら柔軟に経営を舵取りする
農と食の邂逅
- 海道 瑞穂/株式会社アグリたきもと(富山県)
地域の農地を守るために、米のほか大豆やブルーベリーなども作付けする。社員が働きやすい環境を整備し、楽しみながら農業に取り組む
新・農業人
- 藤岡 啓志郎/株式会社AgLiBright(兵庫県)
酒米の王様・山田錦を古くから生産してきた産地で7代目経営者のバトンを受け取った29歳。人を幸せにする農業をめざし試行錯誤を続ける
オピニオン・レポート
フォーラムエッセイ
- 農業の伝道師に
HIRO/お笑い芸人
調査レポート
- 物価上昇で「経済性志向」が13年半ぶりに40%を超える
─消費者動向調査(2023年7月調査)─
主張・多論百出
- 飼料用稲で水田活用と飼料自給率向上を
持続可能な畜産業の推進のためにも必要
元村 聡/一般社団法人日本草地畜産種子協会 常務理事
ぶらり食探訪 ―サンフランシスコ―
- 日本のお酒をイベントで売り込む
堀米 大樹/在サンフランシスコ日本国総領事館 領事
耳よりな話 第248回
- WAGRIが進める農業DX
中川 博視/農業・食品産業技術総合研究機構
地域再生への助走
- 米粉を活用した25年にわたる地域づくり
自治体・企業・市民の総力で普及に努める
箙 活則/胎内市農林水産課(新潟県)
書評
- 『日本は食料危機にどう備えるか ――コモンズとしての水田農業の再生』
金子 弘道/ジャーナリスト
インフォメーション
- 第16回「アグリフードEXPO東京」
~東京で4年ぶりに会場開催~ - 東讃地域で交流会を実施 高松支店
- 農業経営のヒントを得る勉強会 東京支店
- シェフズミーティングで地域ブランドを支援 盛岡支店
- 3県合同で先進事例や最新制度を学ぶ さいたま支店
- みんなの広場・編集後記
農業経営アドバイザー
TiDBit
- 農業は若者にとって挑戦できる業種
秋葉 芳秀/秋葉会計事務所
次号予告
- 次号の特集は、「今こそ問われる養殖業の成長産業化」を予定。全国の漁業生産量の2割程度を占める養殖業。ホタテ貝やブリなど一部品目は輸出に大きな影響を与えており、重要性は高まっている。一方、ウクライナ情勢などを発端とする資材高騰を受け、調達の見直しが迫られるなど情勢に対応した取り組みが必要だ。環境変化による影響を受けるなかで、養殖業の成長産業化に向けた道筋を、事例を交えて考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
撮影:伊東 剛
北海道美瑛町
2018年10月5日
秋まき小麦畑の朝
■整然と並んだ秋まき小麦の新芽が早朝の光を受けて輝く■
帯の色:黄丹色
2023年夏2号「革新促すスタートアップ」
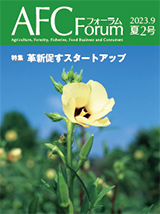
-
電子ブック版(83.7MB)
特集
革新促すスタートアップ
【特集】
- スタートアップの育成で農と食を変革
東野 昭浩/農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究総務官
国の重要政策と位置付けられているスタートアップ育成。農林水産・食品分野でも課題解決の重要手段として注目され、各種施策が講じられている
- データや自動化技術で農業経営を支援
松田 恭子/株式会社結アソシエイト 代表取締役
農業を取り巻く環境が厳しさを増し、農業経営にも進化が求められている。作業効率の改善や収益向上を先端テクノロジーで支援する取り組みに迫る
- ICTが変える産直と青果物流通
金子 弘道/ジャーナリスト
生産者と消費者のかかわりや市場流通の仕組みなど、既成概念を覆す取り組みが進んでいる。流通の構造を変容させ、社会課題解決の可能性をも秘める
巻頭言
観天望気
- 思いつきが世界を変える
合瀬 宏毅/アグリフューチャージャパン 代表理事 理事長 日本農業経営大学校 校長
連載
変革は人にあり
- 小林 晋也/株式会社ファームノートホールディングス(北海道)
農と食の邂逅
- 依田 美奈/ユーザーライク株式会社(東京都)
新・農業人
- 原 充・原 真美/原園芸(佐賀県)
オピニオン・レポート
フォーラムエッセイ
- 生産者と消費者の架け橋に
竹下 裕理/フリーアナウンサー
主張・多論百出
- 可能性秘めたアグリフードのスタートアップ
事業会社との連携が飛躍的な成長のための鍵
有馬 暁澄/Beyond Next Ventures株式会社 パートナー
ぶらり食探訪 ―メキシコシティ―
- サルサなくして味はなし
志賀 大祐/日本貿易振興機構(ジェトロ)メキシコ事務所
耳よりな話 第247回
- 植物専門病院の創立
中島 隆/農業・食品産業技術総合研究機構
地域再生への助走
- 耕作放棄地の現地確認作業を効率化
データの活用で地域の活性化へ道筋
山下 角英/下呂市農林部農務課(岐阜県)
書評
- 『日本の食料安全保障 ―食料安保政策の中心にいた元事務次官が伝えたいこと』
石井 勇人/共同通信アグリラボ 編集長
インフォメーション
- 新しい農福連携を学ぶ 宮崎支店
- 県内新規就農者同士の交流会 高知支店
- きのこ料理の試作会 山形支店
- タイ農業・協同組合省が来庫 情報企画部
- 最先端スマート農業を学ぶ 鹿児島支店
- 耕畜連携に関し情報交換 前橋支店
- 子実コーン産地化を支援 大津支店
- お取引先さま専用サービスのご利用について 新業務企画室
- みんなの広場・編集後記
農業経営アドバイザー
TiDBit
- 農業経営アドバイザーと農業者の付き合い方
林 裕己/未来環境エネルギー計画株式会社
次号予告
- 次号の特集は、「地域の特色を生かした農地活用」を予定。世界の食料供給の不安定化などの環境変化のなかで、平時から国民の食料安全保障の確立に向けた施策が議論されている。主食用米から海外依存の高い麦、大豆、飼料作物などへの転換・生産拡大、実需者との連携による加工用米や高収益作物の導入と定着など、地域の特色を生かした農地活用の事例を取り上げ、生産基盤の強化に向けた在り方を考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
撮影:植原 直樹
山梨県北杜市白州町
2004年9月1日
オクラの花
■夏の光を浴びて咲くオクラの花。レモンイエローが美しい■
帯の色:常盤緑
2023年夏1号「輸出産地が拓く海外市場」
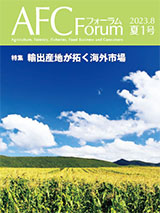
-
電子ブック版(81.3MB)
特集
輸出産地が拓く海外市場
【特集】
- 農産物輸出を牽引する輸出産地の形成
大橋 聡/農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課 輸出産地形成室長
農林水産物・食品の輸出拡大に必要があるのは、産地が一体となり生産から販売までを輸出向けに改善していく。その道筋を農林水産省が解説する
- 生産者と企業が連携するグローバル産地
金子 弘道/ジャーナリスト
生産者と地域の食品企業が連携し、世界市場に打って出る例が各地で見られ始めた。持続的な産地をめざして勝負する二つの取り組みを追った
巻頭言
観天望気
- 日本の魅力を輸出する
蒲生 篤実/日本政府観光局(JNTO) 理事長
連載
変革は人にあり
- 安藤 昌義/なめがたしおさい農業協同組合(茨城県)
昭和の高度経済成長期以来の焼き芋ブームが到来し、日本の高級スイーツとして輸出も増えている。ブームの火付け役に、ヒットの秘策を聞いた
農と食の邂逅
- 吉田 佳代/梅乃宿酒造株式会社(奈良県)
斬新な発想でリキュール梅酒の製造に着手し、輸出にも取り組む。酒蔵を新設し、日本酒造りの見学や体験なども取り入れ日本の文化を発信する
新・農業人
- 丸山 桂佑/アグベル株式会社(山梨県)
前職での経験を踏まえ、農業をビジネスの視点で分析。法人を設立し輸出に取り組む。地域とともにさらなる輸出拡大をめざす
オピニオン・レポート
フォーラムエッセイ
- サハラ砂漠でふりかけを
竹内 海南江/リポーター・ミステリーハンター
調査レポート
- 輸出に取り組む農業者は1割
継続意向はそのうち9割超
―農業者の海外展開の状況に係る調査―
主張・多論百出
- 「成長モデル」が日本の食の理解へ導く
輸出とインバウンドの好循環で成長加速
北川 浩伸/日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO)執行役
ぶらり食探訪 ―バンコク―
- 加熱する日本産食品市場
村上 裕紀/日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所
耳よりな話 第246回
- 輸出拡大を通じた地方創生
田中 健一/農業・食品産業技術総合研究機構
地域再生への助走
- 品質保持技術の進化で輸出拡大
柿生産者と連携し海外でも人気
西島 拓/紀北川上農業協同組合 営農販売部(和歌山県)
書評
- 『日本酒外交 ―酒サムライ外交官、世界を行く』
吉田 忠則/日本経済新聞社 編集委員
インフォメーション
- 地域のお客さま交流会 大分支店
- 地域活性化を考えるオンラインセミナー 甲府支店
- 北陸3県合同の交流会 金沢支店
- 海外輸出の現状を学ぶセミナー 静岡支店
- 新規就農希望者への講義 山形支店
- 地元信用金庫の勉強会に登壇 名古屋支店
- いわて食の商談会2023 盛岡支店
- eMAFFで申請できる公庫資金が増えました 新業務企画室
- みんなの広場・編集後記
- 第16回アグリフードEXPO東京 開催のご案内
次号予告
- 次号の特集は、「農業におけるスタートアップ」を予定。高齢化が進み労働人口の減少が著しい農業界。労働力の確保や生産性向上に加え、農産物の高付加価値化が必須であり、消費者ニーズを的確につかんで生産に反映させることが求められる。外部の視点で対応策を見出し、農業界に革新をもたらし得るスタートアップの潮流や取り組みを、事例を交えて考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
撮影:西島 毅
北海道余市郡赤井川村
2014年8月28日
トウモロコシ畑と夏空
■実りの時期を迎えたトウモロコシ畑。頭上には青空が広がる■
帯の色:豌豆緑
2023年春2号「有機農業の現在地と針路」
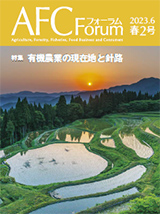
-
電子ブック版(82.3MB)
特集
有機農業の現在地と針路
【特集】
- 食料・農業の持続性向上に向けて
岩間 浩/農林水産省 大臣官房審議官(技術・環境)
みどりの食料システム戦略が本格稼働している。「待ったなし」で環境負荷を軽減するため具体化された、さまざまな支援措置を紹介する
- 企業理念との連携が有機普及のカギ
山田 優/農業ジャーナリスト
小売業・食品製造業に親会社を持ち、有機農業に参入した企業を取材した。手探りで始めた取り組みは、環境に配慮した農業推進のモデルケースだ
巻頭言
観天望気
- ガストロノミーの街から
皆川 治/鶴岡市長
連載
変革は人にあり
- 早川 仁史/新篠津村農業協同組合(北海道)
有機農家への技術指導や販路開拓を全面的に支援している農協がある。みずから有機農業に携わってきた組合長が牽引し、輸出拡大にも取り組む
農と食の邂逅
- 市原 奈穂子/株式会社パストラル
あいがもん倶楽部(熊本県)
病院に勤務していた経験から、食の大切さを痛感し有機農業に取り組む。自然と共に丁寧に作った生産物が、地域や家族で循環する
新・農業人
- 岸川 勉/株式会社きしかわ農園(島根県)
仲間とハウスの栽培団地を形成し、20年前から有機農業に取り組んできた葉物野菜農家。「生業としての有機農業」を成り立たせるため尽力する
オピニオン・レポート
フォーラムエッセイ
- 地球(ほし)と寄り添う
工藤 夕貴/俳優
調査レポート
- 農業景況DIは過去最低値に
食品産業の投資意欲は上昇
―農業景況調査・食品産業動向調査(いずれも2023年1月調査)―
主張・多論百出
- 学校給食への有機農産物の導入加速へ
地域農業と連携して食の持続性を高めよ
小口 広太/千葉商科大学 准教授
ぶらり食探訪 ―ニューヨーク―
- 「だし」が最先端! NY日本食事情
藤岡 洋太/日本貿易振興機構(ジェトロ)ニューヨーク事務所
耳よりな話 第245回
- 節足動物が媒介するウイルス
室田 勝功/農業・食品産業技術総合研究機構
地域再生への助走
- 「オーガニックビレッジ宣言」を策定
官民学が連携して有機農業を拡大
吉岡 秀典/宇陀市農林商工部農林課(奈良県)
書評
- 『国民のための「食と農」の授業 ファクツとロジックで考える』
村田 泰夫/ジャーナリスト
インフォメーション
- 地域の企業が取り組むSDGsの実践事例 鹿児島支店
- 税務や実体験など事業承継を学ぶ 札幌支店
- 林業関係者の交流会 近畿地区総括課
- バスツアーでマッチング 津支店
- 大阪農業の未来に向けて多様な支援 大阪支店
- 東京のフレンチ店で十勝・根釧の食をPR 帯広支店
- 新規就農者に交流の場提供 盛岡支店
- 水産関係者向け講演会 松江支店
- みんなの広場・編集後記
- 第16回アグリフードEXPO東京 開催のご案内
次号予告
- 次号の特集は、「グローカル輸出産地形成が促進する農産物輸出」を予定。政府は、2030年までに農林水産物輸出額5兆円を目標に掲げている。22年は円安の影響や外食需要の回復により、年間1.4兆円と過去最高実績を計上した。しかしこの拡大基調を継続するには、海外のニーズを踏まえた生産・流通の転換が不可欠だ。マーケットインの発想で地域がまとまり形成される「輸出産地」の道筋を、事例を交えて考察する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2023年春1号「持続性を高める耕畜連携」
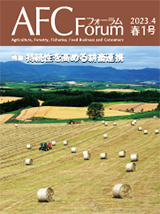
-
電子ブック版(76.1MB)
特集
持続性を高める耕畜連携
【特集】
- 耕畜連携で持続可能な農業モデルを実現
三輪 泰史/日本総研 創発戦略センター エクスパート
飼料・肥料危機に対して、中長期的に輸入依存度を下げる抜本的な対策として「耕畜連携」が注目を集めている。そのポイントと地域への波及効果を解説する
- 先進事例から考える耕畜連携の課題
吉田 忠則/日本経済新聞社 編集委員
苦境に陥っている畜産業。国産飼料の活用により、国際相場の影響をやわらげている先進事例を紹介する。取材から見えてきた現状と課題とは
巻頭言
観天望気
- ウシの事情、消費者の理解
渡辺 好明/新潟食料農業大学 学長
連載
変革は人にあり
- 隅 明憲/有限会社鹿野ファーム(山口県)
輸入豚肉の相場に左右される枝肉価格。耕畜連携で地域と協業し、早くから6次化に取り組む大規模養豚事業者の奮闘する姿から、課題を考える
農と食の邂逅
- 前田 智恵子・齋藤 順子/前田牧場(栃木県)
ホルスタイン素牛肥育に踏み切った大規模稲作農家の父の下で、姉妹で役割分担。大田原市のブランド赤身肉へと育て、循環型農業を模索する
新・農業人
- 式地 優貴(高知県)
中学で畜産を志し、26歳で経営を継ぐ。稲発酵飼料や地域との連携などが支えとなり、厳しい情勢下、未来予想図を描いて踏ん張る
オピニオン・レポート
フォーラムエッセイ
- 鯨のビフテキ
中原 丈雄/俳優
調査レポート
- 「経済性志向」が70歳代を除くすべての年代で上昇する傾向
―消費者動向調査(2023年1月調査)―
主張・多論百出
- 各国で遺伝子組み換え栽培活発化
食料安保へ国内導入の是非検討を
菅 正治/時事通信社 ロンドン支局
ぶらり食探訪 ―ホーチミン―
- 「安くてうまい」にどう挑むか
村田 義剛/日本貿易振興機構(ジェトロ)ホーチミン事務所
耳よりな話 第244回
- 農業経営計画策定支援アプリ
松本 浩一/農業・食品産業技術総合研究機構
地域再生への助走
- 耕畜連携で地域農業を元気にする
エゴマや飼料用米をエサにし養鶏
竹下 正幸・竹下 靖洋/有限会社旭養鶏舎(島根県)
短期集中連載 ご存じですか「飼料」の世界
- 最終回 飼料とSDGs
石川 巧/協同組合日本飼料工業会
書評
- 『ビジネスパーソンのための日本農業の基礎知識』
石井 勇人/共同通信アグリラボ 所長
インフォメーション
- 農業経営の課題を考察 3県合同の研修会 津支店
- 高知県農業の未来へ 関係機関連携の取り組み 高知支店
- 先進事例と行政の施策から県産品の輸出を学ぶ 盛岡支店
- スマート農業の最前線から農業経営のヒントを得る 前橋支店
- みんなの広場・編集後記
- 第16回アグリフードEXPO東京 開催のご案内
次号予告
- 特集は「環境負荷軽減に待ったなしの有機農業」を予定。「みどりの食料システム戦略」で2050年までに全耕地面積の25%、100万ヘクタールに拡大する目標を掲げている有機農業。自然循環機能を向上させ環境負荷を抑える有機農業は、輸出促進に向けても不可逆的な取り組みだ。有機農産物の付加価値に対する理解促進を図るため、小売段階の実情を探るとともに、国内の先進的な事例を紹介する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2023年冬2号「再造林が拓く国産材時代」
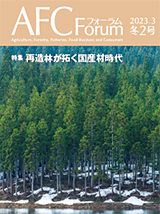
-
電子ブック版(77.9MB)
特集
再造林が拓く国産材時代
【特集】
- 再造林で国産材の安定供給体制を構築
小坂 善太郎/林野庁 森林整備部長
「伐って、使って、植えて、育てる」循環の確立には再造林が不可欠だが、再造林率は3~4割にとどまる。ボトルネックは何か、施策を進める立場から解説する
- 持続可能な木材産業へ進化する条件
遠藤 日雄/特定非営利活動法人活木活木森ネットワーク 理事長
ウッドショックで国産材時代への号砲が鳴った。持続可能な木材産業へ事業者が自力で進化するための課題を示す
巻頭言
観天望気
- 果たすべき役割
戸髙 壽生/佐伯広域森林組合 代表理事組合長
連載
変革は人にあり
- 大田 浩二/公益社団法人徳島森林づくり推進機構(徳島県)
国の制度に先駆け、管理受託制度を始めていたのが旧徳島県林業公社だ。次々と稼ぐ仕組みを生み出し、カーボンクレジットの販売へと手を打つ
農と食の邂逅
- 兵庫 泉/株式会社兵庫親林開発(静岡県)
急傾斜地や特殊伐採など、施業が厳しい現場を新規開拓する女性経営者に林業への思いを聞いた。資源を余すことなく使い切り、「材」を「財」に変えていく
新・林業人
- 瀬川 瑠衣子/富山県西部森林組合(富山県)
ひょんなきっかけから林業の世界に足を踏み入れた女性がいる。森林施業プランナーとして活躍し、森の芽吹きに「循環」を実感する日々だ
オピニオン・レポート
フォーラムエッセイ
- 山と向き合う
田中 陽希/アドベンチャーレーサー
調査レポート
- 多くの業種で経費の増加が見られ始めた2021年
―2021年農業経営動向分析―
主張・多論百出
- 大いに可能性を秘めている日本の林業
森林大国ドイツに学び「稼げる産業」へ
永濱 利廣/第一生命経済研究所 首席エコノミスト
地域再生への助走
- 地域資源の森林を余すことなく活用し
未来につなげる循環型森林経営を実践
伊東 拓馬/下川町 農林課(北海道)
短期集中連載 ご存じですか「飼料」の世界
- 第2回 飼料の安全性
石川 巧/協同組合日本飼料工業会
書評
- 『森林に何が起きているのか 気候変動が招く崩壊の連鎖』
吉田 忠則/日本経済新聞社 編集委員
耳よりな話 第243回
- 大径材の利用を促進するカギ
伊神 裕司/森林研究・整備機構 森林総合研究所
インフォメーション
- 農業経営アドバイザー向け勉強会 札幌支店・松山支店・広島支店
- 海外展開・輸出セミナーで情報提供 鹿児島支店
- 農業者等経営改善セミナー 横浜支店
- 耕畜連携を考える 福井支店・岐阜支店・大分支店
- JA職員向け出張講義 高松支店
- 第16回アグリフードEXPO東京 出展者募集のご案内
- みんなの広場・編集後記
農業経営アドバイザー
TiDBit
- 家業から脱却し事業とすべくアドバイスを
福田 幸博/税理士法人ひだパートナーズ
次号予告
- 次号の特集は、「耕畜連携のあるべき姿」を予定。輸入飼料の安定調達が不透明になるなか、自給飼料経営への転換に向けて変革が迫られている畜産農家。生産物の付加価値向上・地域活性化にもつながる耕畜連携は、生産者・地域にメリットがある。自給飼料基盤の強化へ向けて動きだした耕畜連携の今後のあり方を探る。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。
2023年冬1号「資源高騰と食料システム」
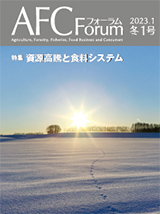
-
電子ブック版(74.4MB)
特集
資源高騰と食料システム
【特集】
- 食料危機の時代に生産力の増強が必要
柴田 明夫/株式会社資源・食糧問題研究所 代表
ウクライナ情勢や気候変動は、資源高騰を長期化させる要因となっている。その構造を読み解くとともに、輸出に依存する日本の食料システム脆弱性を浮き彫りにする
- 国内農業を振興させるサプライチェーン
山田 優/農業ジャーナリスト
食料システム強靭化にあたり、外食産業が国産農産物の実需者として果たす役割は大きい。早くから消費者の潜在ニーズに気付き、産地との連携を進める2社に話を聞いた
巻頭言
観天望気
- 生産者と消費者が思い合う
加藤 百合子/株式会社エムスクエア・ラボ 代表取締役
連載
変革は人にあり
- 若月 一成/若月牧場(千葉県)
生産者の立場から生乳の価値を高めようと、「牛・人・環境にやさしい経営」で資源循環型経営をめざす。だが乳価のコスト増を転嫁する値上げは難しく、その窮状を訴える
農と食の邂逅
- 池谷 千咲/有限会社春華堂(静岡県)
衰退する栗の産地を救う地域ビジネスが立ち上がった。「うなぎパイ」などの銘菓をつくる菓子メーカーとして、付加価値を上げ地元に還元する取り組みを追った
新・農業人
- 矢野 賢太郎/けんちゃんファーム(長野県)
地域農業活性化に向けた行政とJAの取り組みが、県外から移住した非農家出身の青年を「市田柿」の生産者に育てる。周囲に愛され、地域の将来を担う
オピニオン・レポート
フォーラムエッセイ
- かけがえのない食の記憶
大島 花子/シンガー・ソングライター
調査レポート
- 食品産業の景況は持ち直しが続く
原材料の安定確保と価格転嫁に課題
―食品産業動向調査(2022年7月調査)―
主張・多論百出
- 持続可能な食料システム実現のため
消費者が協力「してしまう」仕組みを
下川 哲/早稲田大学政治経済学術院 准教授
短期集中連載 ご存じですか「飼料」の世界
- 第1回 配合飼料と私たち
石川 巧/協同組合日本飼料工業会
耳よりな話 第242回
- ゲノム解析で野菜などの育種を効率化
山川 博幹/農業・食品産業技術総合研究機構
書評
- 『日本のコメ問題 5つの転換点と迫りくる最大の危機』
村田 泰夫/ジャーナリスト
インフォメーション
- 県産品の海外展開セミナー 津支店
- 県産食材の直売イベント 盛岡支店
- 若手農業者に同業者と知り合う機会提供 横浜支店
- 魅力ある農業求人を学ぶ勉強会 千葉支店
- 高校生向け就農セミナー 秋田支店
- 海外金融機関に日本の農業金融を説明 情報企画部
- 北海道の酪農応援マルシェ 帯広支店
- 水産物の輸出を学ぶオンラインセミナー 札幌支店
- 第16回アグリフードEXPO東京 開催案内
- みんなの広場・編集後記
農業経営アドバイザー
TiDBit
- 地域で頼られる存在に
伊藤 亘/税理士法人宮田会計課長
次号予告
- 特集は「続・持続可能な国産材時代へ」を予定。ウクライナ情勢や円安などの影響が続くなか、輸入材は価格高騰や物流面の課題により安定調達に赤信号がともる。戦後に植林され蓄積された森林資源の活用と、再造林に取り組む事例を紹介する。
- *本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。